心筋症とは
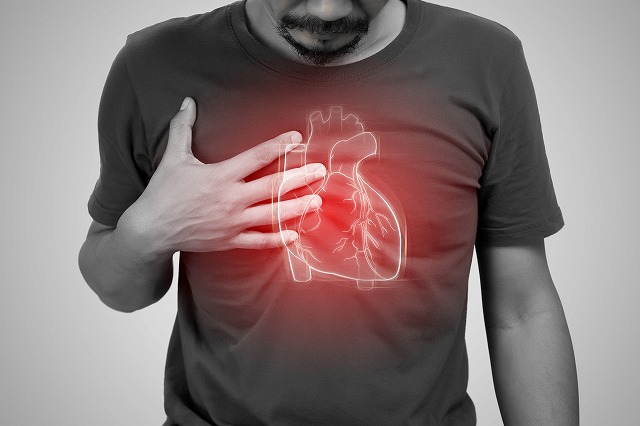 心筋症とは、「心機能障害を伴う心筋疾患」と定義されます。高血圧、心筋梗塞、アミロイドーシスなどのはっきりした原因で発症する「二次性心筋症」とそれ以外の「特発性心筋症」の2つに分類されます。代表的な特発性心筋症には、肥大型心筋症(HCM)と拡張型心筋症(DCM)があります。
心筋症とは、「心機能障害を伴う心筋疾患」と定義されます。高血圧、心筋梗塞、アミロイドーシスなどのはっきりした原因で発症する「二次性心筋症」とそれ以外の「特発性心筋症」の2つに分類されます。代表的な特発性心筋症には、肥大型心筋症(HCM)と拡張型心筋症(DCM)があります。
拡張型心筋症、肥大型心筋症と心不全の関係
心不全とは、心臓が体の組織に必要な血液を十分に供給できなくなる病気です。
息切れ、むくみ、全身の臓器不全などの症状を引き起こし、徐々に悪化して心臓を中心としたさまざまな病気の最終的な結果となる、命を脅かすと言うべき病気です。
心筋症は、心不全に繋がる病気のひとつで、治療の中心は心筋症に伴う心不全の管理と心臓突然死の予防になります。
心筋症の原因はストレス?
たこつぼ型心筋症は精神的・身体的ストレスが原因で起こる病気です。
ご高齢の女性に多く、日常のちょっとした「誰かと激しい口論をした」という程度のストレスでも心筋症を発症するきっかけとなる場合があります。
たこつぼ型心筋症は、過剰な精神的ストレスを受けた結果、心筋の一部がうまく収縮できなくなり、血液を正常に送り出せなくなる病気です。この病名は、心臓がたこつぼ(蛸壺)のように見えることに由来しています。
拡張型心筋症とは
正常な心臓は先が細くなったラグビーボールのような形をしていますが、拡張型心筋症が進行すると、だんだんサッカーボールのような形に膨張していきます。拡張型心筋症では、心筋が薄く伸びてしまい、拡張する能力も収縮する能力も低下してしまいます。家族性の場合が20%程度あると考えられていますが、原因不明のため根本的な治療は心臓移植しかないと考えられてきました。しかし、近年では薬物療法の発達により、心臓移植が必要な症例は非常に限られた場合のみとなっています。
拡張型心筋症の症状
拡張型心筋症は比較的ゆっくり進行すると言われており、心臓や体が変化に適応している場合には、目立った自覚症状がないこともあります。しかし、心筋症の進行が心不全(血液を送り出すポンプ機能に異常をきたす)に繋がると、体は酸素や栄養素が不足した状態になります。
その影響で、疲れやすくなったり、呼吸困難を感じたり、足がむくんだり、手足の冷えを感じるなどの症状が現れることがあります。
拡張型心筋症の検査
拡張型心筋症の診断は、心筋症の原因となる他の病気(高血圧や弁膜症など)を除外することで下されます。このために用いられる検査には、胸部レントゲン検査、心電図検査、心臓超音波検査、そして最近では心臓MRIなどがあります。心臓MRI検査が必要と判断された際には、関連する高度医療機関をご紹介いたします。
肥大型心筋症とは
心筋(心臓の筋肉)が異常に肥大する病気です。心筋が肥大しすぎると、①心臓の拡張が不十分になる(拡張障害)、②左心室から大動脈への通路が狭くなり、全身に血液を送るポンプに異常が起こるなどの症状が現れます。症状がある程度進行するまで自覚症状がない方もいますが、心不全の重症化や、心臓突然死などが比較的よく見られる合併症です。
肥大型心筋症の症状
心筋症の重症度によっては、自覚症状が全くなく、健康診断で偶然発見される場合も多いことが知られています。
一方、自覚症状がある場合には、心房細動などの不整脈に伴う動悸、運動時の息切れ、胸の違和感(圧迫感)などを自覚します。特に深刻な症状としては、脳への血流不足による失神、心房細動による血栓が脳の血管を詰まらせる脳梗塞、心室頻拍や心室細動といった命に関わる不整脈などがあります。
肥大型心筋症の検査
肥大型心筋症の診断は、心筋症の原因となる他の病気(高血圧や弁膜症など)を除外することで下されます。この検査には、胸部レントゲン検査、心電図検査、心臓超音波検査、そして最近では心臓MRI検査が用いられます。心臓MRI検査が必要と判断された際には、関連する高度医療機関をご紹介いたします。
心筋症の治療
従来では、心筋症は不治の病と考えられていましたが、ここ10年ほどの研究開発により、治療法が確立されつつあります。
薬物療法
 心筋症の治療では、適切な薬物治療が不可欠です。特に、β遮断薬、ACE阻害薬、アンギオテンシン受容体拮抗薬(ARB)は治療の柱となる薬剤です。
心筋症の治療では、適切な薬物治療が不可欠です。特に、β遮断薬、ACE阻害薬、アンギオテンシン受容体拮抗薬(ARB)は治療の柱となる薬剤です。
β遮断薬は、心臓を交感神経の過剰な刺激から守り、心不全の進行を防ぎます。
ACE阻害薬は、血圧を下げながら心臓への負担を軽減し、心不全から心臓を保護します。ただし、空咳の副作用がある場合には、同じ作用を持つARBに切り替えることが可能です。これらの薬剤は、大規模臨床試験で心不全患者さんの再入院率や死亡率を低下させる効果が確認されています。それ以外にもさまざまな薬があり、症状に合わせて使い分けます。詳しくは医師にご相談ください。
心筋症のなかでも心アミロイドーシスやFabry(ファブリー)病などの心筋症は治療方針が他の心筋症と大きく異なるため、上記が疑われる場合には千葉大学医学部附属病院などの専門施設にご紹介する方針としています。
ペースメーカー・
植込み型除細動器
 ペースメーカーは、心拍数低下による倦怠感や失神を引き起こす徐脈性不整脈の治療法です。一部の心筋症では、左脚ブロックを伴って心不全が悪化することがあります。左脚ブロックでは心臓の収縮効率が低下するため、両心室ペースメーカーで効率を改善します。また、心筋症では心室性不整脈を合併しやすく、心臓突然死の原因となります。そのため、リスクが高い方などにはAED機能を備えた植込み型除細動器が推奨されます。ペースメーカーの埋込が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介させていただき、ペースメーカー埋め込み後のフォローに関しては、当院ペースメーカー外来にて相談していただけます。なお、植込み型除細動器付きペースメーカーは当院外来では対応しておりません。
ペースメーカーは、心拍数低下による倦怠感や失神を引き起こす徐脈性不整脈の治療法です。一部の心筋症では、左脚ブロックを伴って心不全が悪化することがあります。左脚ブロックでは心臓の収縮効率が低下するため、両心室ペースメーカーで効率を改善します。また、心筋症では心室性不整脈を合併しやすく、心臓突然死の原因となります。そのため、リスクが高い方などにはAED機能を備えた植込み型除細動器が推奨されます。ペースメーカーの埋込が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介させていただき、ペースメーカー埋め込み後のフォローに関しては、当院ペースメーカー外来にて相談していただけます。なお、植込み型除細動器付きペースメーカーは当院外来では対応しておりません。
心臓弁膜症の治療
心臓弁膜症の僧帽弁閉鎖不全症は、心筋症に合併して起こることがあります。心臓の機能が低下して左心室が大きくなると、僧帽弁輪が広がって僧帽弁閉鎖不全症が起こります。これが悪化すると、心不全の症状がさらに進行します。そのため、心臓弁膜症が問題となっている場合は、弁の修復や人工弁の置換が必要になることがあります。
心臓リハビリテーション
いわゆる「心リハ」とも呼ばれる心臓リハビリテーションは、心臓病の患者さんの体力回復、社会復帰・職場復帰の支援、心臓病の再発防止、快適な生活の維持を目的とした治療法です。従来、心臓病の患者さんに対しては「安静第一」が基本的な考え方でしたが、安静にしすぎると心臓病に悪影響を及ぼすことが明らかになってきました。心臓病の患者さんでも適度な運動を継続することで、心臓病の長期予後を改善し、再入院の予防を目指せます。






